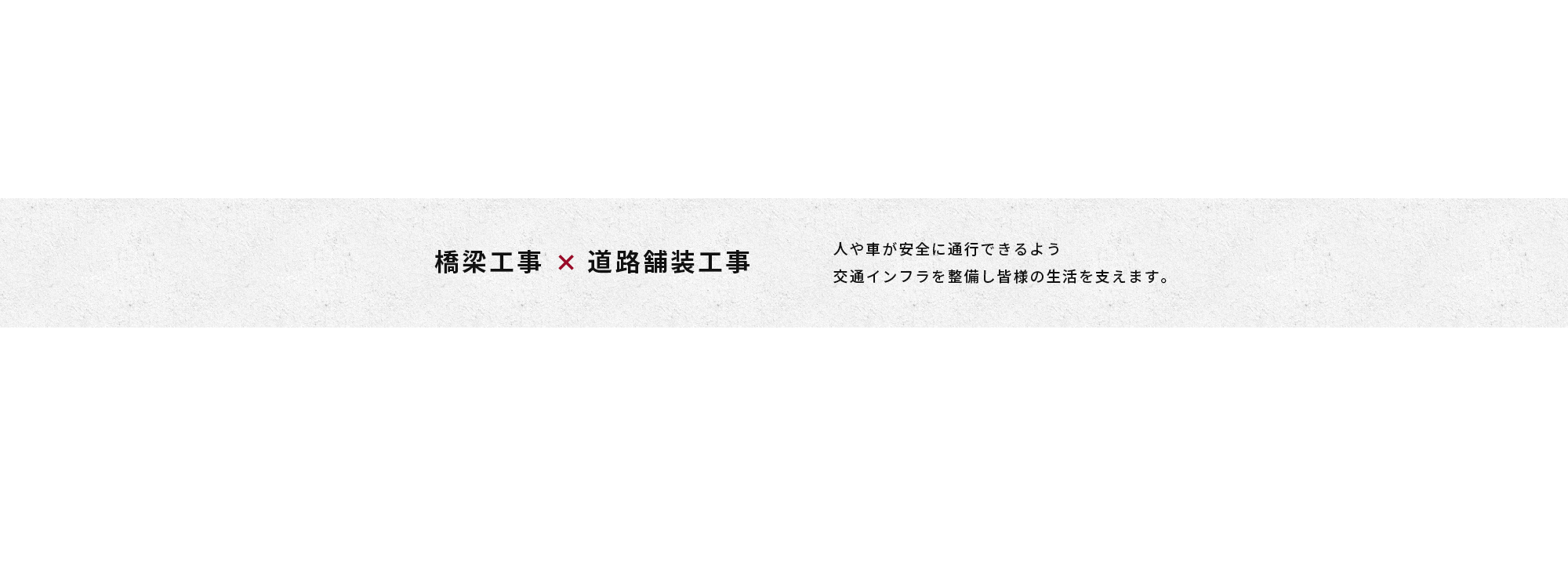橋梁工事の補修・調査・診断は株式会社大泉工業へ!

橋梁工事とは、橋を架け渡す工事です。
そもそも「橋梁」は、川や渓谷道路や鉄道などを渡るために架けられる構造物を指します。
橋梁工事の中には、作った橋の維持やメンテナンスをする橋梁補修工事も含まれます。一口に橋と言っても、桁橋、吊り橋、アーチ橋、ラーメン橋など、様々な橋が存在します。
これらの橋を掛ける工事を総称して橋梁工事と呼びます。
橋を架けることは、街と人を繋げ、より発展した地域づくりの役割を担っています。長く使われる橋だからこそ、未来を見据えてより強度な橋作りが求められていきます。災害の多い日本だからこそ、インフラ設備は非常に重要なものです。
橋梁工事一覧
高度経済成長と共に道路整備が進み、現在までに多くの橋が建設されました。
橋上の安全・円滑な交通を確保し、沿道や第三者へ被害を及ぼすことのないように、橋の耐荷力の保持や耐久性を向上させ有効に橋を活用する行為が即ち維持管理であります。
維持管理において維持、点検、調査、補修・補強そして記録は維持における一連のながれになります。株式会社大泉工業は橋梁の点検、調査、補修・補強を行っています。

断面修復工法(吹付工法・左官工法・充填工法)
コンクリートの劣化部分をハツリ除去し、断面修復材にてコンクリート断面を復元する工法です。
断面修復工法の実施にあたっては、設計図書に示された補修箇所だけでなく、施工前調査を行い、外観調査および打音調査などからコンクリートのはく離・はく落部や浮き部を確認して施工します。
補修材料は、躯体コンクリートより同等以上の強度で、躯体との付着強度も規定を満足する材料が選定され、補修材料の高耐久性が要求されます。

ひび割れ補修工法
コンクリートの微細なひび割れに対し、注入により補修する工法。主にゴム加圧式の低圧注入工法で行い、注入材は目的に応じエポキシ樹脂等の接着力の高いものから、超微粒子セメント系の材料を使用します。
注入を実施することで、一体化による強度回復・劣化因子の侵入抑制等の効果があります。
ひび割れ補修において最もスタンダードな補修工法であり、劣化要因・補修目的に応じさまざまな注入材を選択できます。

剥落防止工法
主にコンクリート床板・トンネル覆工面等、コンクリート片の脱落を防止する工法です。
中性化・塩害・アルカリ骨材反応等によりコンクリートの劣化が進行すると、コンクリート部材の一部が剥落する危険性もあり、第三者被害を招く可能性もあります。コンクリート構造物の表面に特殊樹脂とネットを組み合わせて施工することで、塩分・水・酸素・炭酸ガス等の劣化因子の浸入を抑制するとともに、コンクリート片の剥落を防止することができます。
表面保護工法
コンクリート構造物の表面に用途に応じた被覆材を塗布することで、コンクリートの劣化因子となる塩分・水・酸素・炭酸ガス等の外部からの浸入を抑制し、中性化・塩害・アルカリ骨材反応等の劣化対策において非常に有効な工法です。
表面被覆工法には、有機系被覆と無機系被覆があり、対象となるコンクリート構造物の環境条件や予測される劣化要因に応じて、最も効果的な工法を選定することができます。
表面含浸工法
コンクリート表面に含浸材を塗布することによって、コンクリート表層部の組織の改質、コンクリート表層部への特殊な機能の付与などを実現させ、構造物の耐久性を向上させる工法です。
施工が簡単で短期間で行える。比較的安価。外観がほとんど変わらないため、施工後も目視による点検が可能。紫外線による劣化を受けにくい。施工の際に発生する産業廃棄物の量が少ない。というメリットがあります。
重防食工法
重防食工法は、ニッシン・ジャパンが独自に開発した工法です。コンビナートや海沿の施設に設置されている様々な配管や鋼材のサビや損傷を補強・修復し、加えて長期間劣化を防止するために特殊防食テープを使用し、美装のための仕上げ処理を施す工法です。
火気を使用しないので安全で、どのような環境でも施工可能。 作業時間の短縮と工期の短縮を実現。硬度、強度に優れる。耐候、耐熱、耐薬品性に優れる。というメリットがあります。
電気防食工法
コンクリート中にある鋼材の腐食が電気化学的反応であることに着目し,鋼材が腐食する際に発生する腐食電流を電気の供給によって 断つことで腐食を停止させる手法です。
厳しい腐食環境にある鋼材の腐食を停止できるため,塩害,中性化が進行した構造物に有効です。電気の供給は,コンクリート表面からコンクリート内部の鋼材に向けて継続して行います。防食電流の供給方法や陽極材の形状,陽極システムの設置方法などによって選択できる多様な方式があります。
一般外観変状調査、非破壊試験
既設橋梁等の構造物の調査は、当社にお任せください。
補修・補強設計の内容や現地の状況に合わせて最適な調査方法を採用します。
調査の基本は近接目視です。あらゆる方法を駆使して対象部材に近接します。
ひびわれ、うき、はく離・鉄筋露出といった外観変状調査は近接目視で行います。種々の機材を使用して調査対象部材に近接した状態で、目視により変状の種類と程度とを確認します。現場ではスケッチや写真として記録し、持ち帰ったデータは損傷図やそれに対応した損傷写真として整理します。
アンカー孔削孔の場合など、RCレーダーで鉄筋コンクリート中の配筋状況を確認します。非破壊調査にて行います。